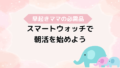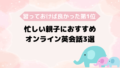主婦の皆さん、毎日の食事作りお疲れ様です。
仕事や育児をしながら、毎日2食または3食のご飯を作るのは本当に大変ですよね。
栄養バランスや好き嫌い、調理の手間を考えながらの料理は一苦労です。

筆者も、家事の中で料理は好きではないので、献立を考えるのも作るのも苦手です。
「1汁3菜」が理想的な品数とは聞きますが、なかなかそうも言っていられないのが現実ですよね。
そんな時に、たまたま「せいろ」が時短料理の味方になる、という投稿を読みました。
せいろといったら、中華料理で肉まんや小籠包の器として出てくるイメージですよね。

「ていねいな暮らし」を代表する調理器具で、ズボラママは縁のない調理器具だという認識でした。
しかしこの投稿を読むと、せいろを使うことで汁物と副菜が一緒に出来る、と書いてあるじゃないですか。
1度の調理で2品出来るなんて、忙しいママたちにとってなんと朗報なんでしょう、と思い、せいろについて調べてみました。
 | 価格:3180円~ |
せいろを勧める理由
ご存じかとは思いますが、せいろについて簡単に説明します。
せいろは、木で出来た蒸しカゴです。

せいろのカゴの中に野菜や茶碗蒸し、肉まんなど、蒸したい物を入れ、沸騰したお湯が入った鍋の上で蒸気によって温め調理します。
投稿を読むまでは、「わざわざお湯を沸かして、その上で調理をするなんて面倒」と思っていました。

しかし味噌汁を作る鍋の上にせいろを乗せれば、味噌汁と蒸し物を一度に調理出来るという投稿は目からウロコでした。
筆者は味噌汁(汁物)だけはかろうじてほぼ毎日作っているので、その上で蒸し野菜が出来れば、1汁1菜が一度に出来るのです。
蒸し野菜であれば、生野菜よりもかさが減りますので、子供にもたくさん野菜を食べてもらえるかもしれません。
せいろの使い方
せいろを使った蒸し野菜の調理方法は本当に簡単で、せいろを水で濡らし、中に野菜を入れるだけ、ただそれだけです。
沸騰したお湯の上にせいろを置き、数分そのまま放置するだけで蒸し野菜の完成です。

野菜の種類によって蒸し時間は変わりますが、野菜を蒸すのと同時に味噌汁の具に火を通しています。
野菜をゆでると栄養が水に溶けてしまう、というのはよく聞く話ですよね。
せいろの中で野菜を蒸すことで、野菜のうまみが逃げずに栄養が閉じ込められるのです。
せいろの魅力を最大限に活かすには、茶碗蒸しやシュウマイなど王道の蒸し物を作る事だと思いますが、ひと手間加える料理は忙しいママにはハードルが高いのが事実です。

その点蒸し野菜であれば、野菜を切ってせいろに入れるだけでほぼ完成のようなものです。
付け合わせの野菜が1つ出来れば、あとは肉なり魚なり、メインを作れば1汁2菜が出来ますよね。
理想はもう一品ですが、無理をしても続かないので、ミニトマトを置くなり、ウインナーや卵焼きを焼くなり、すぐ出来るものを副菜としています。
毎日1汁3菜を作っている私、と思うと、自己肯定感が上がる気がします(笑)

料理上手な方は料理がストレス解消になったり、1汁3菜を作るのも短時間で作れたりすると思いますが、ズボラの料理が苦手なママからすると、「1汁3菜」というワードがとてもストレスなのです。
せいろがあれば、味噌汁と蒸し野菜の同時調理で1汁1菜が出来るので、ストレスも減り、時短になります。
味噌汁とせいろを使っている間にメインを作ったり、他の家事を少しでも進めたりと、有意義な時間の使い方が出来ると思います。
せいろの保管方法
せいろを使った料理が時短で品数が増やせることはご理解いただけたと思いますが、せいろって保管が難しいんでしょ?と思われる方もいると思います。

筆者はズボラママですが、2ヵ月間ほぼ毎日せいろを使っています。
木で出来ているせいろですので、最も気を付けないといけないのはカビです。
せいろは洗剤で洗わずに、水洗いや布巾で拭いて汚れを落とします。
水洗いで大丈夫?と思われがちですが、材質が木ですので、洗剤を使うと木に浸透してしまいます。
肉類を蒸す場合は葉物野菜を敷いたり、クッキングシートを敷く必要があります。

そもそも蒸気を浴びて調理しているので、蒸気による殺菌が出来ているため、水洗いや拭き取りで充分だそうです。
ちなみに筆者は野菜しか蒸さないので、油汚れとも無縁です(笑)
さて、水気を切った後は、風通しの良い所で吊るして乾燥させます。
筆者は、S字フックにかけて、窓の枠にかけて乾燥させています。

しっかり乾燥させているので、今のところカビは生えていません。
いまや毎日使う調理器具なので、使いやすいように出しっぱなしにしています。
出しっぱなしでも、せいろが目の届く範囲にあると、丁寧な暮らしをしている人っぽくなりますよ(笑)
難しそうと誤解されがちなせいろですが、水洗いのあと吊るして乾燥という単純作業で、意外とズボラな保管方法でOKなのです。
せいろを選ぶ時の注意事項
せいろを使うメリットや、意外と簡単に使える、とお伝えしてきましたが、ここからはせいろを選ぶ上での注意事項をお伝えします。
せいろは、沸騰したお湯の入った鍋の上に乗せるだけ、とさんざんお話ししてきましたが、そもそもどんな鍋?どうやって乗せるの?と疑問を持つ方もいると思います。
せいろで使う鍋は、どんなものでも大丈夫です。

ただ、せいろ本体と鍋の大きさが合っていないと使えません。
大きすぎても乗らず、小さすぎてもバランスが悪いです。
せいろに対してピッタリの鍋があればいいですが、ない場合はどうしたらいいのか。
答えは、蒸し板を利用することです。

 | 価格:990円~ |
せいろと鍋の間に蒸し板を挟むと、せいろの焦げ付きを防ぐこともできますし、蒸し板があることでせいろが安定します。
せいろのサイズと鍋のサイズを確認した上で、蒸し板のサイズを選びましょう。
では、せいろのサイズはどれくらいがいいのか。
筆者は、味噌汁を作る用の鍋の大きさに合わせて直径15センチのせいろを購入しました。
 | 価格:693円 |
家族4人分の付け合わせを作るにはとりあえず事足りるかな、という大きさです。
1段15センチのせいろだと、基本的には1人用サイズになりますので、茶碗蒸しや肉まんといった大き目の蒸し物は、1つしか入りません。
欲をいえばもう少し大き目の方が、付け合わせの野菜がたくさん作れますが、「味噌汁と同時に蒸し野菜を作る」が本来の目的ですので、目的は達成出来ました。

現在は1段のみの使用ですが、今後子供が大きくなるにつれて食べる量が増えたら、せいろをもう1段買い足そうかな、と考えています。
せいろを購入する際は、作れる量を重視するのか、家にある鍋が使える大きさを重視するのか、自分がせいろを使う目的を考えた上で、サイズを選ぶといいと思います。
筆者のように、汁物と副菜を同時に調理することを目的とする方は、いつも使っている汁物用の鍋に乗るせいろのサイズを選んでくださいね。
最後に
使い方や手入れが難しそうと誤解されがちなせいろですが、実は忙しいママにこそ使ってほしい調理器具です。
最近せいろを使っている、と周囲の人に話すと、結構な割合で「せいろ気になってたんだよね」という声を聞きます。

気になってはいるものの、使い方や手間がかかりそうで手を出せなかった、という声が大半です。
興味を持ちながらも、扱いづらそうなイメージから使われないことの多いせいろですが、実は思っているよりもハードルが低く、忙しいママの味方だということがお分かりいただけたと思います。
切った野菜を入れて汁物を作る上で蒸すだけ、手入れは手で洗って乾かすだけ、手間いらずで時短が叶う、せいろを使って時短料理しましょう。
 | 価格:3380円~ |